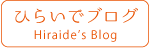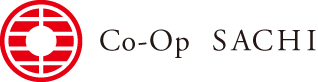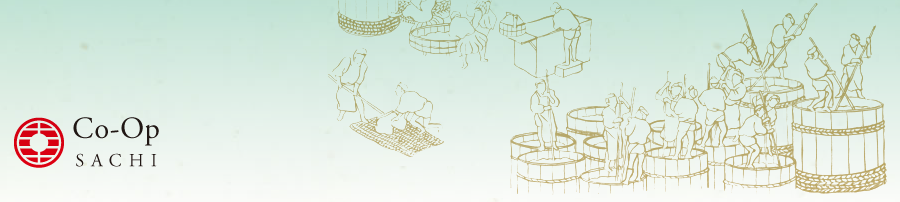2012年7月15日
2012年7月15日

http://www.kusudawines.com/japanese/index.htm
彼が世界レベルのピノノワールを目指して一家でニュージーランドに移り住み、
初めてのヴィンテージを世に出して今年で10年になりました

JALのファーストクラスご用達、採用と聞いた時には本当に嬉しかったです
そのすぐ後にジャンシス・ロビンソンがフィナンシャルタイムスの彼女のコラムに
楠田さんのワインの大絶賛記事を書いた時の事も思い出します
彼のワインは日本の誇りです 
今年9月に10年の節目の会を企画しています
私はもちろん実行委員の一人でございます
2012年7月14日

来日中の弟と銀座「祢保希」で土佐料理を堪能中、
かつおの塩たたきと天然鮎に弟は大喜びでした
http://r.gnavi.co.jp/g688000/
弟は台湾で「乾杯」という焼肉店を経営しています
小さい時から大変な食いしん坊でした
http://www.kanpai.com.tw/index.htm
2012年7月11日

前回大好評だったリッツカールトン東京のメインダイニング「Azure45」で
第二回の日本酒と本格フレンチの会が行われました

山形県「出羽桜」仲野社長、福井県の加藤吉平商店「梵」の加藤社長、愛知県「蓬莱泉」の関谷社長が参加され、今回も参加者の皆さんから「大満足!」のコメントが続々でした


この企画前まで全く日本酒と接点のなかったという本格フレンチの荒木シェフ
(合計8年2回の渡仏経験をお持ち)が真剣に日本酒に向き合って作ってくださった
メニューは今回も大変素晴らしいもので感動でした

メニューに関しては今後の日本酒の海外進出を見据えて
「あえて日本風にしないでフレンチの本流にそった内容のもの」
という風にお願いしていました

当日参加された方々はそれを感じていただけたと思います
2012年7月6日

料理通信8月号が発売です
今月は今年のIWCで純米酒トロフィを獲得した
大信州酒造の「大信州 N.A.C.」をご紹介しています
http://www.daishinsyu.com/

今年のIWC日本酒審査会に審査員として参加してくださった
レストランロージェのシェフソムリエの中本さんにコメントをいただいています

皆様、是非ご一読くださいませ
2012年7月5日

スマートフォン専用の登録読者向けメールマガジンサービス
「酒ゼミ」の19回目配信です

今回は女性蔵元の尾畑酒造の尾畑留美子さんが
「日本酒クールスタイル」についてのコラムを

そして酒ゼミ編集部の田畑さんが
「日本酒フェア2012」のイベントレポートを

今週ご紹介の蔵元さんは愛知県の「蓬莱泉」と茨城県の「郷乃誉」です

読者無料登録ですのでスマフォユーザーの皆さま、
是非ご登録くださいませ
http://sakezemi.com/index.php
2012年7月5日

リニューアルした料理通信のWebページで
3月に行ったリッツカールトンのメインダイニング「Azure45」での
日本酒の会を特集で取り上げていただきました

食のシンクタンクと自負する料理通信の編集による本格記事です。
ご注目ください
http://www.r-tsushin.com/

海外に日本酒が進出するという事は
和食以外の食事と日本酒とが楽しまれる世界になっていくという事ですが、
(日本ではいち早くワインと寿司、天ぷら、懐石などを楽しんでいます)
それをきちんと食の専門家が言語化したものは、
実はあまりないのではないかと思います
この記事はそういう意味でも意味のあるものですね

http://www.r-tsushin.com/
2012年7月4日

観光庁の滝本地域振興部長が発起人をされ東北酒蔵ツーリズムから地域振興、
そして被災地支援へという会を開催しました

蔵元さんも7名駆け付けてくださり

東北各県、そして茨城と新潟の県の東京事務所の方々はじめ

霞が関からは観光庁の井手長官、国税庁審議官、経済産業省地域グループ審議官、
総務省自治財政局長、
外務省や国家戦略室からも参加してくださり、

省庁連携で日本酒振興への暖かい輪が出来上がったような会でした

会場はアトムリビングテック様がご提供くださり

お酒やおつまみも各県で持ち寄り、

参加者の会費でまかなう手作りの会は
終了予定が大幅に伸びて素晴らしい余韻でした
2012年7月2日
IWCの日本酒審査に参加してくださった酒文化研究所代表の狩野卓也さんが
酒造組合中央会主催の「日本酒で乾杯推進会議」のメルマガのコラムに
今回の審査を通じてのご感想を丁寧に書いてくださいました。
*************************
■日本酒コラム「国際化のための他流試合」
6月も最終週となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。今月は、直前に迫ったロンドンオリンピックの代表決定戦や、サッカーW杯ブラジル大会の最終予選などスポーツに関する報道が目白押しでした。ここ一番の試合で実力を十分に発揮できた場合とうまくいかない場合などいろいろあった中で、サッカーの場合には、2勝1分とこれ以上ない順調な滑り出しでした。テレビで試合を見ていても昔に比べると明らかに強さと余裕を感じさせられます。なぜこれほど力をつけてきたのかと言えば、国内だけにとじこもらずに、海外の強豪リーグでプレイして経験値の高い選手が増えたからなのでしょう。仮に技術的には同じ程度であったとしても他流試合をこなした選手は、瞬間的な判断能力があがっているのでしょう。考えてみれば、日本の製造業が隆盛を極めた頃も商品や人がどんどん海外に出ていき、国内だけよりも多様な価値観による判断を受け入れて、商品開発、改良などを進めていたのではないかと思います。
国際化という意味では、日本酒の世界でも同じようなことが起きています。日本酒の海外出荷はじわりじわりと増加してきましたが、ここでも国際化のために他流試合が寄与しています。たとえば、ワインの世界では最も有名で規模も最大のコンテストIWC(International Wine Challenge)というものがあるのですが、関係者の努力によって2007年から日本酒部門も設けられています。ロンドンで行われる世界的なコンテストですので審査員も半分以上は外国人です。したがって、同じように日本酒をティスティングして評価を決めるのであっても手法や評価軸がずいぶんと違います。今年はこの審査会が東京で行われたので、私も審査員をさせていただきましたが、一言でいえば、そのお酒の長所を言葉で表し、その価値観が他の審査員と共感できるかどうかがポイントとなります。
日本で行われてきた日本酒の審査は、製造上の欠陥がないかを確認して良好な味わいになっているかを確認することが主流で、長所を見つけ出すということには、重きをおいていませんでした。日本人は謙譲を美徳とするので、あまり褒めるということが得意ではないという気質も反映されてきたのかもしれません。しかし、外国の人に受け入れてもらうためには、素晴らしさ、おいしいさを簡潔に外国語!で表現できないとそもそも飲んでもらうことができません。だから日本酒のおいしさ、香り、そして乾杯の作法や意味などの表現、用語をもっと考えないといけません。
とりあえずは、ワインの世界で使っているフルーティ、フルボディなどの用語をそのまま日本酒の表現でも使っている人が多いようですが、いまひとつしっくりきません。できれば日本酒オリジナルの評価用語が生まれてほしいものです。そしてそれが柔道用語のように、そのまま海外で使えるようにできたら最高だと思いませんか。日本酒が海外で飲まれるようになると同時に「Kanpai」「Tanrei」などの言葉と意味が世界中に広がるようにするために、もっといろいろな人と盃を重ね、乾杯をしていきたいものです。
(日本酒で乾杯推進会議運営委員・酒文化研究所代表 狩野卓也)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
http://www.sakedekanpai.jp/member/index.html
2012年7月1日

時評(行政情報の総合誌)7月号が発売になりました
http://www.jihyo.co.jp/index.html

連載させていただいている「日本酒だより」では
新潟県新発田市の市島酒造をご紹介しています
http://www.ichishima.jp/

市島社長とはずっと酒サムライ活動をご一緒していましたので、
ついついその事を書いてしまいました
2012年6月28日

スマートフォン専用の登録読者向けメールマガジンサービス
「酒ゼミ」の18回目配信です

前々回から初めて審査を日本で行ったIWC2012のSake部門について
「審査の裏側」としてコラムをご紹介しています
読者無料登録ですのでスマフォユーザーの皆さま、是非ご登録くださいませ
http://sakezemi.com/index.php