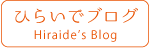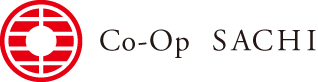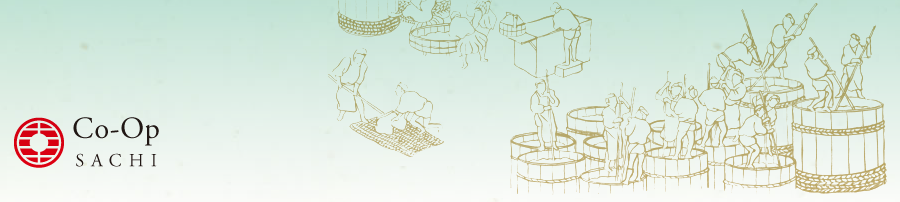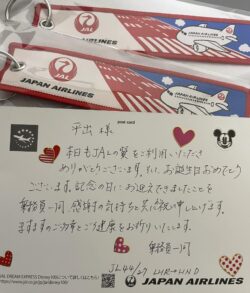日本酒造青年協議会 第90回通常総会
2023年5月11日令和5年(2023年)若手の蔵元の全国組織、日本酒造青年協議会(前垣壽宏会長)の第90回通常総会に出席しました。私は、平成18年(2006年)から酒サムライコーディネーターというお役をいただきこの会のお手伝いをしています。
総会は、オンライン参加も可能での開催でした。
議事進行はスムーズに進んで、来賓ご挨拶を、酒造組合中央会の岡本副会長からいただき総会は終了。
総会後の講演は、2019年に富山県に新しく出来た蔵、IWAのシャルル・アントワン・ピカールCEOにお話しいただきました。https://iwa-sake.jp/ja/
そして、その後は、首都圏在住の酒サムライの方々もご一緒に交流会が行われました。
第一回の酒サムライ叙任者の歌手の加藤登紀子さんも参加くださり、和気あいあいと参加蔵元の皆さんのお酒で乾杯致しました。